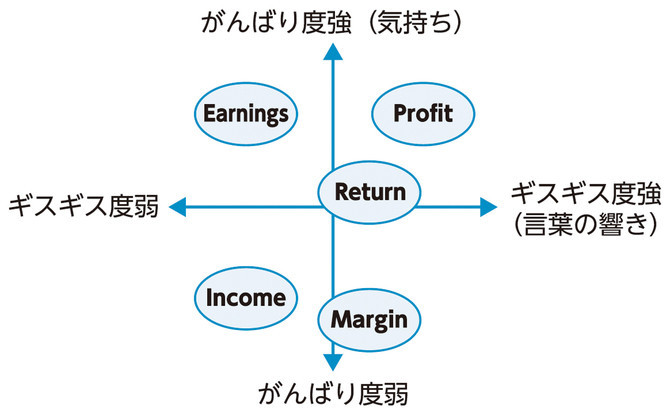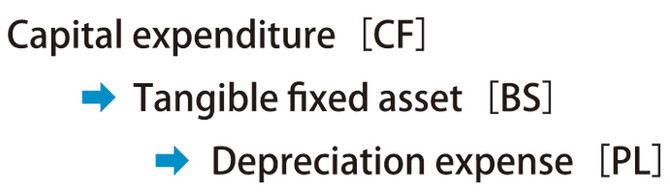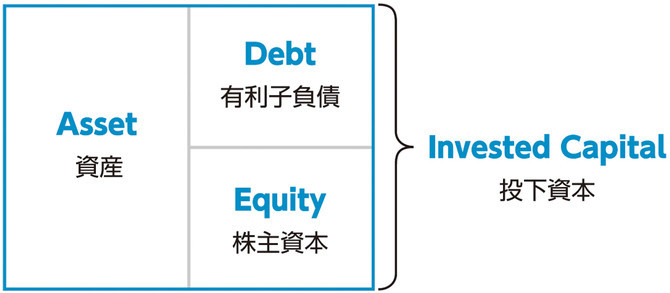米国株の情報などを得ようとすると、避けて通れないのが会計や投資関係の英語です。しかも、日本の用語と一対一にはなっていないんですね。使い分けされている場合が多々あります。
そこで、財務諸表関係から投資指標関係、投資商品関係の英語を調べてまとめてみました。
財務諸表を読むときの英語
BS(貸借対照表)では、それぞれこのような英語になります。
資本:Equity
借入:Liabilities
資本:Asset
でも普通の会話で借入、負債はDebtと呼ぶことも多いです。例えば負債比率は Debt Ratioですね。
P/Lはもっとややこしいですね。売上はRevenueとSalesの両方がありますが、Revenueのほうが広い意味合いのようです。利息や配当金なども含めてRevenueで、純粋なビジネスによる売上はSalesだということのようです。
売上:Revenue/Sales
利益はさらにいろんな言い方があります。ちょうどイメージ図で書かれた記事がありました。
利益:Profit/Income
営業利益率:Operating Margin
紛らわしい会計英語を整理しよう | 会計プロフェッショナルの英単語 | ダイヤモンド・オンライン
コストは、P/LでいうのかBSでいうのかで違うようです。
P/Lのコスト:Expense
BS上のコスト:Cost
しばしば会話に出てくるのが「CAPEX」です。これはCapital Expenditureの略で、資本的支出、つまり設備投資です。
設備投資:CAPEX
そして減価償却は、有形か無形かで違う表現になります。
有形固定資産の減価償却:Depreciation
無形固定資産の償却費:Amortization
投資家が気にする英語
投資家がレポートを読んだり検索するときに必要な英語もいろいろとあります。配当はDividendです。"ex-devidend"となると、配当落ちです。"ex-devidend date"は「配当落ち日」になります。
配当:Dividend
利回りはYieldです。でもReturnとも言いますね。ちょうどいいネイティブの解説がありました。
利回り:Yield/Return
Return is retrospective (past); dealing with things that have already been made or collected.
Yield is prospective (future); dealing with things that will be made or collected.
なるほど、過去の実績についてはReturn、将来の利回りについてはYieldだということでした。よく債券のYieldといいますが、これは債券の利回りは将来のものだからですね。逆に、ファンドの成績など過去の利回りはReturnです。
自社株はTreasury Stockです。直訳すると宝の株です。日本語の金庫株みたいな感じでしょうか。
自社株買い:acquisition/purchase of treasury stock(s)
資本はEquityだと思っていましたが、Capitalとも言いますね。何が違うの? と思って調べたら、CapitalはDebtも含んだ調達した資金全体を指すようです。
ちなみに発行済株式数×株価を時価総額(Market Capitalization)といいますが、企業価値というときはEV(Enterprise Value)を使う場合もあります。こちらはMarket Capに、有利子負債(Debt)を足して現預金(Cash)を引いたものですね。なぜCashを引き、Debtを足すかというと、「この会社を買収するのにいくらかかるか?」を示すものだからです。Cashが多い会社ならその分買収金額は少なくて済みますし、Debtが多ければその分金額が必要なので足し込むわけです。
増資:Capital increase
時価総額:Market Cap
企業価値:Enterprise Value
株主はShare Holders。単にHoldersとも書くようです。
株主:Holders
では株式はどうでしょう? これはStockとも言いますしShareとも言います。EPS(Earnings per Share)というときはShareですね。慣例で変わるようですが、ニュアンス的にはこうなるようです。
出資者それぞれのequityを簡単に表すために、彼らの出資金合計である資本金(capital stock)を等分したひと切れ(share)を株式(a share of stock)と呼びならわすようになったのです。
株式:Stock
株式分割:Stock split
優先株:Preferred stock
投資商品を指す英語
株式はStockですが、広い意味で証券というときにはSecuritiesです。警備会社はSecurityですが、証券は複数形だそうです。日本だと「◯◯証券」の英語名として「◯◯ Securities」と書いてある場合が多いです。一方で、米国の証券会社は、「Investment Bank」(法人相手)だったり「brokerage firms」(個人相手)だったりします。
株式:Stock
証券:Securities
証券化:Securitization
投資信託は2種類の呼び方があるようです。実ははっきりとしなかったのですが、どうやら途中解約が可能なオープンエンド型の投資信託はMutual Fundと呼ぶのが普通のようです。日本語でもファンドと呼びますね。一方で、解約不能のクローズエンド型の投資信託もあります。こちらはInvestment Trustと呼ぶようです。例えば、REITは"Real Estate Investment Trust"です。REITはShareを他人に売却はできますが、解約はできませんので、なるほどという感じではあります。
投資信託:Mutual fund(オープンエンド)/Investment Trust(クローズエンド)
債券もややこしいですね。基本はBondのようですが、米国債はTreasuryで、しかも期間によって名前が変わります。
債券:Bond
米国債:US Treasury
米国短期国債:Treasury Bills(T-Bills)
米国中期国債(〜10年):Treasury Notes
米国長期国債(30年):Treasury Bonds
不動産関係はこんな感じのようです。住宅ローンはMortgateなので、それを証券化したものはモーゲージ債なんて呼ばれますね。
不動産:Real Estate
投資用不動産:Commercial property
マンション:Apartment/Condominium
ワンルームマンション:Studio apartment
敷金:Deposit
住宅ローン:Mortgage
居住者:Resident
住居用:Residence