前回、株式の節税マニュアル(1)として、基本的な考え方を説明しました。金融商品への課税は、損益通算できる箱が3つ(+1)あること。そして節税の方向性としては、(1)税繰り延べ(2)控除枠と経費の活用(3)税率の違いの活用 があることを簡単にまとめました。
今回は、2つ目の「控除枠と経費の活用」について実際の例を書いてみます。
- 総合課税と法人の控除枠と経費を活用する
- 雑所得も経費が使える
- 法人は経費の王様
- 箱から箱へ利益を移転する:法人から雑所得へ
- 株の利益を別名義へ
- 株の利益を別名義へ2
- 株の利益と先物の利益を移転する
- 超上級技
総合課税と法人の控除枠と経費を活用する
税金は利益から経費(控除)を引いた残りにかかるので、経費や控除枠があるところで利益を発生させれば、その分税金を減らすことができます。3+1の課税の箱の中で、これが(実質的に)存在するのは、総合課税と法人です。
総合課税のほうは、人的控除として48万円の基礎控除が存在します。給与所得者なら、年間で48万円以上の給与を受け取っているでしょうから、追加の金融所得にこれは使いようがありません。ただし、例えば子どもなどは別です。
子どもの口座で、20万円の利益が出た場合を考えてみましょう。まず、15%(※復興税除く)の所得税については、年間20万円未満の利益については確定申告の義務がありません。つまり、特定口座を使わず一般口座にしておけば、20万円未満の利益なら税金がかからないわけです。ただし5%の住民税については、別途申告は必要になってしまいます。
では30万円の利益が出た場合はどうなるでしょう。このときは確定申告を行えば、48万円の基礎控除で相殺されて、やはり課税利益はゼロ。これは配当だけでなく譲渡益も対象です。

※株の税金|株取引でかかる税金と節税対策|freee税理士検索
雑所得も経費が使える
総合課税として計算されるものの1つに、雑所得があります。投資家にしばしば関係する総合課税の内訳としては次があります。
- 給与所得
- 不動産所得
- 雑所得
このうち、1と2は損益通算が可能。そのため、不動産で損失(帳簿上の。減価償却とかが損失になるので)を出せば、給与所得から差し引くことができ、税率を下げられます。(3)の雑所得については、残念ながら(1)や(2)と損益通算ができません。ただし、雑所得内での損益通算は可能です。
雑所得(総合課税)に該当するものは、投資関連だと次のものがあります。
- 仮想通貨
- ソーシャルレンディング
- 貸株
- ブログなどの副業
これらについては、利益と損失を合算して通算できるわけです。そして、株式投資などに比べれば、雑所得は経費が認めやすい。例えば、仮想通貨のハードウェアウォレットは当然経費だし、ブログなどの副業には経費がつきものです。副業が赤字になれば、それは仮想通貨などの利益からマイナスできることになります。
仮想通貨の税金を減らす方法はこちらにまとめました。
また雑所得の経費をどう作るかは、下記にまとめています。
法人は経費の王様
法人も豊富に経費を使える箱です。自宅をオフィスに使っているなら、家賃やローン支払い額の一部を按分して経費にできますし、水道光熱費通信費なども按分対象。業務で利用するPCや書籍なども経費になり、これらは株式の利益から差し引けます。
もちろん、法人に貯めた現金は、個人に移転するときに再び所得税が取られるので、ここでまた基礎控除を活用したり、退職金控除を活用したりといろいろと考える必要はあるのですが、さまざまな経費が使えることは、これを超えるメリットがあります。
箱から箱へ利益を移転する:法人から雑所得へ
さて、実際にこれらのメリットを享受するには、利益を移転しなくてはなりません。株式で得た利益を、子どもの利益に移し替えたり、法人の利益に移転する必要があります。どうやって利益を移転するか? これが今回のキモです。
まず法人と個人雑所得間の利益移転は、個人と法人の間で契約を結んで役務を提供するのが手っ取り早いです。例えば、個人で所有しているクルマを法人に貸し出して、レンタル料を払ってもらえば、その費用は法人側では経費となり、個人側では雑所得になります。個人側では、この役務を提供するにあたり商売道具としてクルマを保有しているので、クルマの減価償却が可能になります。200万円の4年落ち中古車なら、2年償却なので1年あたり100万円の経費となる形です。
利益移転だけでなく、雑所得の経費も作り出せる技です。
株の利益を別名義へ
ちょっとややこしいのが、株式の利益移転です。節税目的としては、個人から子どもなどの口座に移転したり、経費が使える法人口座への移転ですね。まずは経常的に行える方法から。
ちなみに、法人は取引責任者が自分だし、未成年の子どもの場合親権者が取引主体者になります。名義貸しではないので、念のため。もし専業主婦の口座と行いたい場合は、事前に打ち合わせて、売買を本人にやってもらう必要があります。
株式の利益移転では、基本的にクロス取引を使います。信用口座を開きやすい個人側で信用売りを行い、同時に子どもの口座や法人口座で現物を買います。すると、異名義間でクロスが完成し、全体として見れば株価の動きに資産額が左右されなくなります。しかし、これだけだと個人から子ども/法人へ利益が必ず移転できるわけではなく、値動によっては逆になってしまう場合もあります。
そこでタイミングが重要です。その銘柄の配当権利確定日を狙うのです。するとどうなえるか。
- 個人側 配当落調整額の支払い
- 子ども/法人側 配当の受け取り
と、配当分だけは確実に移転ができるわけです。仮に配当額が2%だとすれば、100万円の資金でも年6回くらい回転させて行うだけで、12万円を移転できます。それなりの資金があれば、けっこう動かせるわけで、実際ぼくは毎年個人口座側で数百万くらいの損失を作っています。
さらに、この構図はよく見るとまさに優待の異名義クロスであることが分かります。個人側で売りを建てて、子ども/法人側で優待と配当を取得する形です。こうした優待銘柄は権利確定日に向けて上昇する場合が多く、相場状況にもよりますが、意外と譲渡益についても利益移転ができてしまったりするものです。
株の利益を別名義へ2
やり方は一緒ですが、譲渡益のタイミングを見てポジションをクロースすることで、利益を移転することもできます。
- 個人側 信用売り
- 子ども/法人側 現物買い
のクロスを建てておいて、うまくその銘柄が上昇したら、信用売りを反対売買、現物を売って、全部のポジションをクローズします。そうすれば、譲渡益分が移転できるわけです。
この方法はシンプルですが、「うまく銘柄が上昇」がキモで、逆方向に動いてしまっては目が当てられません。また、クロスは信用売りにコストがかかるので、あまり長期間ポジションを保有するのはよろしくない。というわけで、イザというときの手段と考えておく方がいいと思います。
株の利益と先物の利益を移転する
同じ狙いとして、株の利益と先物の利益を移転するという方法もあります。こちらも、両側でクロスを作って、狙った方向に動いたらクローズというのは同じです。
ぼくもそうですが、株で利益が出ていて、でも先物で損失がある(またはその逆)という状況はしばしばあります。それぞれ損失の繰り越せる期間は3年なので、タイムリミットが迫ったらなんとか損失を解消したいもの。そのため、こうした利益移転が必要になるわけです。
すぐに思いつくのは、日経225の先物と日経225ETFでクロスをする方法です。ただ、これには1つ問題があって、板寄せの時間が異なるんですね。クロスする場合、寄付か引けのタイミングで成行注文を出すのが定番です。板寄せという仕組みによって、買いでも売りでも成行ならば同じ価格で約定するからです。
ところが、株は9:00/12:30寄付、11:30/15:00引け、一方で先物は8:45/16:30寄付、15:15/6:00引けというように、タイミングが違っています。これでは、同じ価格での約定ができません。
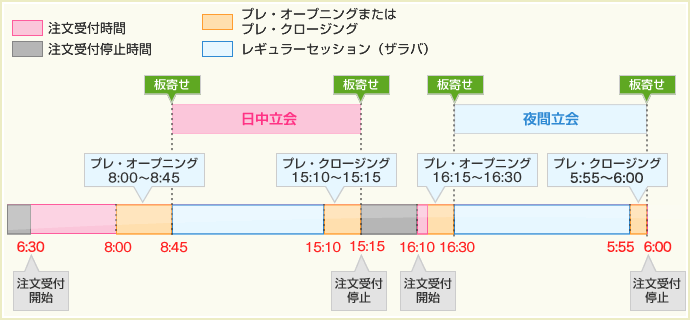
こちらは何かいい方法がないものか。詳しい人のご指摘を待ちたいと思います。なお日経平均CFDはほぼ24時間取引でき、板寄せもないので、やはり同値でのクロスは難しいかと。
超上級技
なお、先物の箱には、FXやCFD、オプションなども含まれますが、このオプションを使う超上級技もあります。というのも、海外証券会社の株式オプション(売り)は、権利行使されると現物の株式が割り当てられるからです。これをうまく使うと、オプションを現物株に変換できます。
残念ながら、国内サクソバンク証券のオプションは権利行使されるとCFDポジションになってしまうし、日経平均オプションはSQが来るとSQ価格で強制決済されてしまいます。そのため、このような技は使えない(と思う)のですが、このあたりはマニアックなほど複雑なので、素敵な技も存在するのかもしれません。